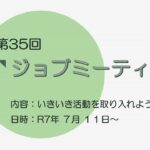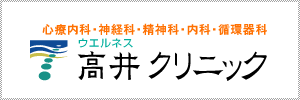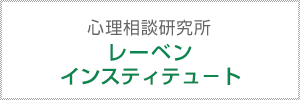児童発達支援事業所・放課後等デイサービス そよかぜきっず 「サービス重要事項説明書」
あなたに対する利用サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて、医療法人 明萌会 が説明すべき事項は次の通りです。
1.サービスを提供する事業者
| 法人の名称 | 医療法人 明萌会 |
|---|---|
| 法人の種別 | 医療法人 |
| 事業種別 | 児童発達事業所・放課後等デイサービス |
| 法人の代表者 | 理事長 髙井 昭裕 |
| 法人の電話番号 | 0575-23-8877 |
| 法人の設立年月日 | 平成11年2月10日 |
2.事業の運営
| 施設の種類 | 多機能事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス) |
|---|---|
| 施設の名称 | そよかぜ |
| 指定事業所番号 | 2150200356 |
| 指定年月日 | 児童発達支援 令和5年2月1日、放課後等デイサービス 令和6年6月1日 |
| 主たる事業所 | 〒501-3932 岐阜県関市稲口760番地4 |
| 電話番号 | 0575-36-1950 |
| 事業所 | 〒501-3932 岐阜県関市稲口760番地4、岐阜県関市稲口774番地4(事業所及び会議室) |
| 管理者 | 小瀬木 新八 |
| 児童発達支援管理責任者 | 渡邉 佳世 |
| 主たる対象者 | 18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者等 |
| 利用定員 | 10名 |
| 通常事業の実施地域 | 関市(その他要望のあった地域も行うものとする。) |
| 開始年月日 | 児童発達支援:令和5年2月1日、放課後等デイサービス:令和6年6月1日 |
| 第三者評価実施状況 | なし |
3.サービスの目的 ・ 運営方針
| 目的 | 医療法人明萌会(以下「事業者」という)が設置する「そよかぜ」において実施する障害児通所支援事業の指定児童発達支援(以下指定児童発達支援という)、同じく障害児通所支援事業の指定放課後等デイサービス(以下指定放課後等デイサービスという)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援及び、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という)の意思及び人格を尊重して、常に障害児及び保護者の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。 |
|---|---|
| 運営方針 | 1.指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供にあたっては、事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2.指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供にあたっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 3.前2項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という)及び「岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定児童発達支援等を実施するものとする。 |
| 事業の運営 | 指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、保護者の負担により、事業所の職員以外の者による介護は行わないものとする。 |
4.サービスに係わる施設 ・ 設備等の概要
医療法人明萌会は多機能事業所そよかぜとして、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所を運営しています。
(1)施設の概要
主たる事業所
| 建物 | 構造 | 木造建て |
|---|---|---|
| 延べ床面積 | 192㎡(内、1階部分、2階部分ともに96㎡) |
(2)主な設備
主たる事業所(2階 児童)
| 活動室 | 1部屋 |
|---|---|
| 相談室 | 1部屋 |
| 個別療育室 | 1部屋 |
| 洗面設備 | 1か所(3区画あり) |
| 便所 | 大人用 1か所 児童用 2か所 |
| シャワー室 | 1か所 |
5.サービス提供職員の配置状況
| 職種 | 専従 ・ 兼務 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 兼務 | 1 | 1 | 管理者・サービス管理責任者 | |
| 児童発達支援管理責任者 | 兼務 | ||||
| 保育士 | 専従 | 1 | 1 | ||
| 児童指導員 | 専従 | 1 | 2 | 2 | |
| 機能訓練担当職員 | 専従 | 1 | 0.6 |
6.各職種の勤務体系 (常勤の場合)
| 職種 | 勤務体系 |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者 | 事業所が定めるシフトに基づく(休憩1時間) |
| 保育士 | 事業所が定めるシフトに基づく(休憩1時間) |
| 機能訓練担当職員 | 事業所が定めるシフトに基づく(休憩1時間) |
| 児童指導員 | 事業所が定めるシフトに基づく(休憩1時間) |
7.サービス提供日とサービス提供時間
| サービス提供日 | 事業所が定める予定表に基づく |
|---|---|
| 休日 | 事業所が定める予定表に基づく |
| サービス提供時間 | 月曜日・水曜日・金曜日 9:00~18:00(個別療育はこの限りではない) 火曜日・木曜日 9:00~15:30(個別療育はこの限りではない) |
8.サービス提供の内容
(1)障がい児給付費対象サービス内容
1.児童発達支援計画の作成
2.日常生活訓練(日常生活動作、歩行、音楽活動等)
3.集団生活適応訓練(会話、SST等)
4.機能訓練(理学療法、作業療法、言語療法、心理指導等)
5.創作的活動(絵画、工作、園芸等)
6.社会生活上の便宜の提供(レクリエーション行事等)
7.生活相談
8.保護者指導
9.健康指導
10.前各号に掲げる便宜に附帯する便宜(1~9附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言)
9.保護者から受領する費用の額等
指定児童発達支援を提供した際には、保護者から指定児童発達支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとします。法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付いたします。
(1)次に定める費用については保護者から徴収いたします。
1.日用品費:実費
2.創作活動に係る材料費:実費
3.その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるもの:実費
4.前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとします。
5.1~3までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付いたします。
(2)利用料金 障がい児通所給付費
1.0歳から満3歳になった後の3月31日までは、利用料の1割負担があります。
*世帯所得に応じて月ごとの上限負担額があります。
2.満3歳になった後の4月1日以降は、利用料負担はありません。
3. 放課後等デイサービス利用者は、利用料の1割負担があります。
*世帯所得に応じて月ごとの上限負担額があります。(受給者証に記載あり)
(3)利用料のお支払い方法
利用者の負担金は請求書をお渡しします。 当事務所に 直接お支払いください。
10.サービス利用に当たっての留意事項
(1)体調不良その他の理由で通所予定日に通所ができない場合には、朝9時までに連絡すること。
(2)施設利用中に体調が悪くなった場合は、速やかに職員に申し出ること。
(3)通所途中又は帰宅途上で事故等にあった場合は、速やかに連絡すること。
(4)住所、連絡先、世帯状況、その他身辺状況に変動があった場合は、管理者に届け出ること。
(5)備品・設備等は丁寧に取り扱い、損傷もしくは故障した場合には、速やかに職員に連絡すること。
(6)建物・備品・設備等に損害を与えた場合は、施設に対して損害賠償を行わなければならない場合もあること。
(7)他の利用者に身体的・精神的・物的損害を与えた場合は、当該利用者に対して損害賠償を行わなければならない場合もあること。
11.サービスの概要
すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所の児童発達管理責任者が作成し、保護者の同意をいただきます。尚、「個別支援計画」の写しは保護者に交付いたします。
12.利用者の記録及び情報の管理等
(1)当事業所は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。ただし、サービス提供を行う上で、他の事業所及び医療機関との連絡調整や市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
13.緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに以下の医療機関へ連絡を行います。
| 医療機関名 | ウェルネス高井クリニック |
|---|---|
| 院長名 | 高井 昭裕 |
| 所在地 | 岐阜県関市稲口774番地4 |
| 電話番号 | 0575-23-8877 |
| 診療科 | 心療内科・精神科・内科 |
14.要望・苦情申立先及び虐待防止に関する相談窓口
【1】要望・苦情申立先
当事業所が提供したサービスに関して要望・苦情がある場合は、いつでも申し立てることができます。
また、以下に記載されている機関に苦情を申し立てることができます。
1) 苦情解決責任者 浅野 隆 (かざぐるま 施設長)
2) 苦情受付担当者 中島 千晶 (かざぐるま 指導員)
0575-21-5566
3) 第三者委員 (1) 木村 恵子 中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 准教授
0575-46-7126
(2) 重戸 俊次 岐阜市社会福祉事業団 指定特定相談支援事業所 所長
058-252-0936
4) 苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出るこ ともできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助 言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
医療法人明萌会で解決できない苦情は、岐阜県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
運営適正化委員会連絡先 電話 058-278-5136
FAX 058-278-5137
5) 虐待防止に関する窓口 各市町村虐待防止センター
【2】虐待防止の措置
本事業所では利用者に対する虐待を早期に発見し迅速かつ適正な対応を図る為次の措置を講じています。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定 虐待防止責任者 施設長 浅野隆
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 従業員に対する虐待防止の啓発、普及するための研修会の実施
15.身体拘束の禁止
(1)事業所は、サービス提供にあたって、利用者又は、他の利用者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
(2)事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その必要事項を記録する。
(3)事業所は、身体拘束の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる
16.非常災害時の対策
| 非常時の対応 | 別途定める「そよかぜ消防計画」により対応いたします。 |
|---|---|
| 平常時の訓練 | 別途定める「そよかぜ消防計画」に基づき年2回、出火を想定した避難・防災訓練を利用者も参加して実施します。 |
| 防災設備 | 火災警報器・消火器 |
| 消防計画 | 防災管理者 : 田中耕爾 |
17.当事業所のご利用にあたり留意いただく事項
| 外出 | 事業所から外出する際は、事前に職員に連絡してください。 |
|---|---|
| 設備と器具の利用 | 事業所内の建物や設備、器具は本来の用途にしたがってご利用ください。 これに反して器物破損が生じた際は、賠償していただくことがあります。 |
| 貴重品等持ち物の管理 | 保護者および利用者の責任において管理していただきます。 貴重品の持参は控えてください。 |
| 宗教活動・政治活動・営利活動 | 保護者および利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
| 動物飼育 | 事業所内へのペットの持ち込みは禁止します。 |
18.契約の終了
①利用者は【そよかぜ】の利用契約を終了する場合は30日以上の予告期間をおいて文書にて事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。
②事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には利用者は直ちに契約を解除することができます。
(1)事業者もしくはサービス提供担当職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
③事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し10日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。
④利用者が以下の事項に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
(1)保護者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を2か月以上滞納し期間を定め、再三催告したにもかかわらず支払いがない場合。
(2)利用者が故意または重大な過失により事業者もしくはサービス提供担当職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用していただくことができない場合。
(5)利用者が連続して6か月を超えて利用がない場合。
(6)利用者が連続して6か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して6か月を超えて入院した場合。
(7)利用者が死亡した場合。